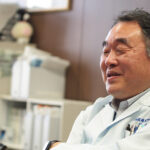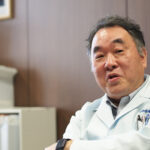シャワーを浴びるように臨床を続ける

中根:鍼灸師には、臨床あるいは研究という2つの道がありますが、先生は臨床を経験し、その後、研究者としての道を進まれますよね。
どういった経緯で、臨床の道へ入られたのでしょうか?
矢野:理療科教員養成科施設を卒業する際に富山に…、あ、ぼくは富山県出身でね。富山はいま白エビが最盛期で、その前はホタルイカ、その前は紅ズワイガニ・寒ブリが美味しくて…ぜひ1度富山には遊びに来ていただきたいですね…。「いい人、いきいき、キトキトの魚」と言いましてね、新鮮なものが溢れかえっております。あ、今日はケンミンSHOWの話をしにきたんじゃなかった(笑)。
中根:(笑)。
矢野:ええと…卒業後はですね、富山盲学校の理療科教員として働くために、帰ろうと思ったんです。兄は東北大医学部内科に勤めており、富山には帰らなかったのです。兄とはひとつ違いの兄弟でした。
おふくろは、兄が帰らなかったことから、私に帰ってきてほしいと思っていたようで、そのときの殺し文句が、「吉永小百合にそっくりの女性がいるから、会いに来い」というもので、ついついその言葉に気持ちが揺らいで、よし帰ろうかなと(笑)。
しかし、教員になるにしても、臨床経験がほとんどないままであったことから、果たして臨床指導ができるのか…、その不安が日に日に膨らみ、意を決し、主任教授の芹澤先生に相談に行きました。「臨床経験のないまま、富山で教員としてやっていくことはできない。ぜひ研究室に残してください」と。そして、芹澤先生の許可を得て、研究室に籍をおき、附属の臨床室で朝から晩まで臨床三昧の日々を過ごしました。
生活費は、専門学校の教員として勤務し、なんとか稼ぎながら、日々、シャワーを浴びるように臨床を続けた2年間でした。その過程で生意気にも「少しは臨床できるようになったんじゃないか」という、そんな感覚があって、臨床することが非常に楽しくなった時期でした。
中根:「シャワーを浴びるように臨床を続ける」って、名言ですね。
矢野:やはりね、週1回の臨床を何年も続けるよりも、短期間で集中するのが、1番臨床力を身につけることができるのかな、と、自身の経験上、今も思っています。
明治鍼灸大学の大学1期生が卒業する時、若手人材養成として、「臨床研修鍼灸師」という制度ができました。当時、大学院を設置することがまだできない状況で、その代替案として「臨床研修鍼灸師」が創られました。環境的には附属病院も開設され、鍼灸の基礎、及び、臨床研究を推進させようとする勢いがキャンパス内にみなぎっていました。私は内科担当ということで配属され、附属病院、及び、鍼灸センターで臨床研修鍼灸師とともに朝から晩まで、ここでもシャワーを浴びるように臨床しました。
臨床研修鍼灸師の学生をみていると、2年経ちますと、鍼灸の臨床力が飛躍的に伸びることを実感しました。臨床力は、時間経過に比例して伸びてくるのではなく、一定の時間(臨床経験)が経過した時点で一気にジャンプするような形で力が伸びるわけです。
それには、だいたい2年間、かかります。その後にドンッと伸びるんですね。そういったことから、週1回や2回といったように、ダラダラと臨床をしていても、あまり伸びない。集中的にやるほうが、確実に臨床力を磨けるのではないかと確信し、そのことを学生や研修生、院生にも伝えてきました。
医療人のひとりとして
中根:会場に集まってくださっている皆さんは、これから鍼灸師としての人生を歩もうとしている人達ばかりですが、「こういう人は、研究よりも臨床に向いている」というポイントはありますか?
矢野:難しい質問ですね…、臨床が好きな人は、医療人のひとりとして、少しでも患者さんの役に立ちたい、患者さんの問題を解決したい、という思いやりを持っています。患者に寄り添うといった姿勢ですね。
わたしがまだ鍼灸を習い始めた学生時代に『文藝春秋』を読み、とても印象に残ったことがあります。その内容はアメリカの医学部の入試に関する内容でした。
その記事によると、アメリカの医学部では、入試の際に、約1ヶ月ほど医学部の教授と面接してマインドとして医師の資質、つまり患者に寄り添う姿勢などがあるかを見極めるという内容でした。その中で例として取り上げられていた事例です。とても印象的でした。
筆記試験でトップを取った学生であっても、面接の結果、医師としての資質がないと判断され、不合格にされたという内容でした。その学生は翌年も受験し、再度トップを取ったのですが、やはり医師としての資質がないと判断されました。しかし、あまりにも頭脳が良いということで、「あなたは医師として向いていないが、基礎研究者として進むのであれば」との条件でようやく入学が許可されたということでした。その記事を読んで、日本の医学教育が、こういう形にならないものか、と思ったのです。
患者の”患”という字は、串に心、すなわち「心が串刺しになった状態の人」が患者さんであるということです。患者さんは、病苦を背負って病院にやってくる人なのですから、医療者は、その病苦にどれだけ傾聴し、寄り添うことができるのかが大切だといえます。
アメリカでは、どれだけ入試の成績が良くても、医師としての資質があるかどうかを丁寧に見極わめ、合否判定をしていることに感動しました。その記事を読んだとき、アメリカのそういうところがすばらしいと記憶に残りました。日本もそうあるべきではないかと思いました。
NEXT:明治時代は、日本伝統医学の分岐点