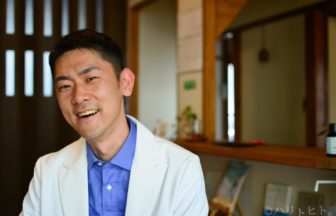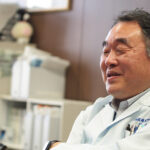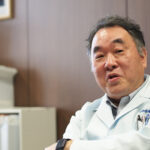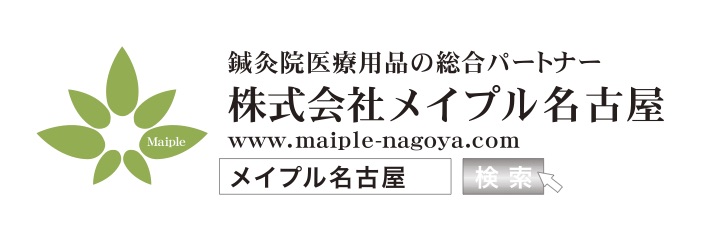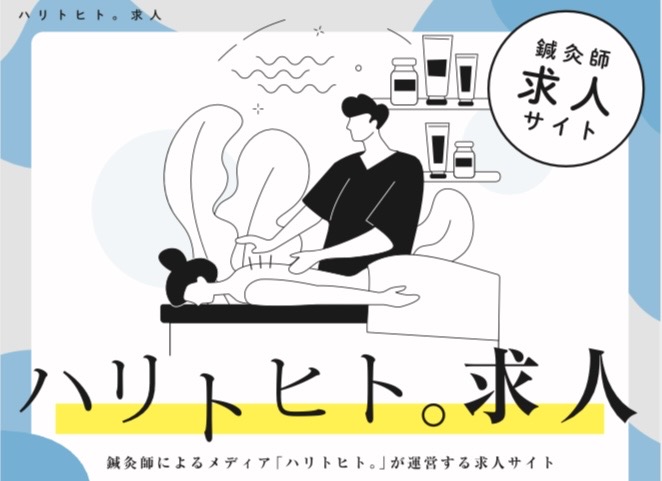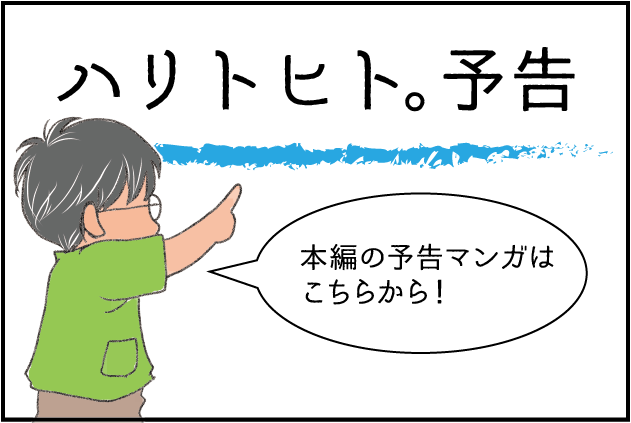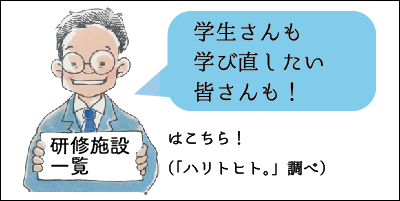鍼灸院を地域コミュニティの拠点にしよう
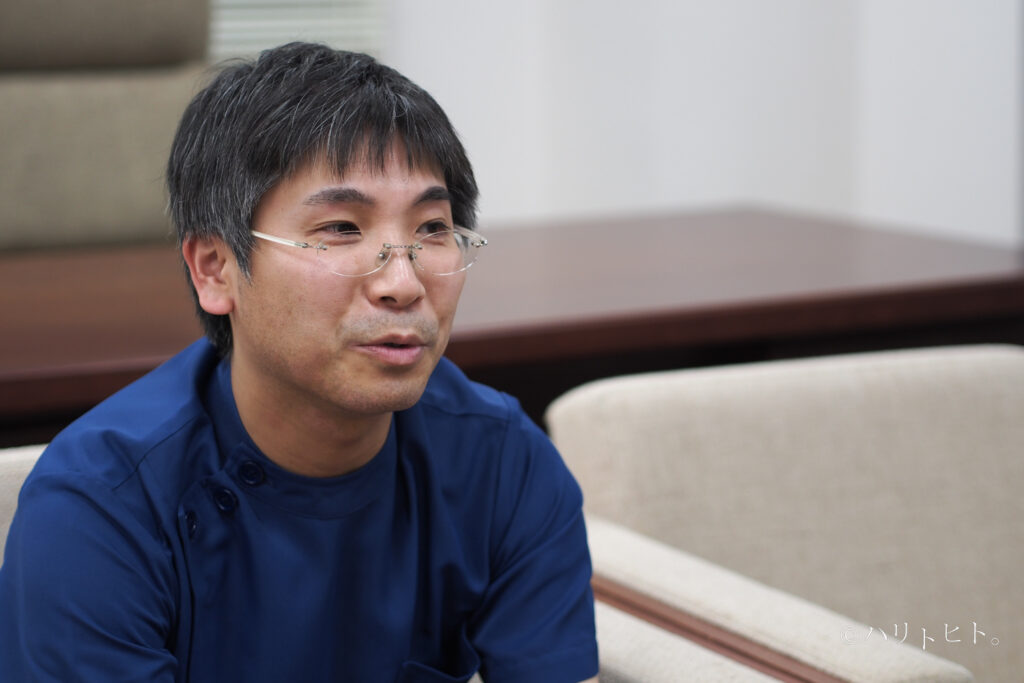

山﨑先生
鍼灸の技術以外のところでさらに言えば、開業鍼灸院は地域のコミュニティの1つとしても、今後より重要になってくると考えています。
お互いに信頼できる関係性やつながりを重要な資源とする「ソーシャルキャピタル」の考え方が今、注目されてきていますものね。
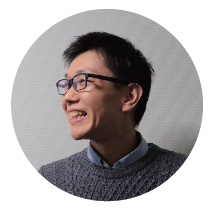
ゆうすけ

山﨑先生
身体のつらい症状について、情報交換したり、治療を受けたり、セルフケアを教わったりする…といったコミュニティの中心に、鍼灸院が位置づけられると理想的ですよね。
私は祖母の代から60年近く同じ場所で鍼灸院を開業しているんですけど、自分が育った地元で子育てをしているという患者さんも多くて、世代間を超えた交流が自然とおこなわれているんですね。患者さんとの雑談で「新しい店ができたよ」と街の情報交換をしたりもします。「コミュニティの場としての鍼灸院」というのは、すごくよくわかります。

タキザワ

山﨑先生
海外だと「ソーシャルアキュパンクチャー」といって、広場に10人ぐらいを座らせて、合谷と百会など数カ所に鍼をして帰る、というような機会があるそうです。
自分の苦痛について人に話す機会って、あまりないじゃないですか。でも苦痛が自分だけのものになると、人はいっそう苦しむようになります。「実は膝が痛くて」「私もなのよ」というやりとりができれば「自分だけじゃないんだ」と苦痛の共有化が図られて、慢性痛も起こりにくいといわれています。
自分の苦痛について人に話す機会って、あまりないじゃないですか。でも苦痛が自分だけのものになると、人はいっそう苦しむようになります。「実は膝が痛くて」「私もなのよ」というやりとりができれば「自分だけじゃないんだ」と苦痛の共有化が図られて、慢性痛も起こりにくいといわれています。
私の鍼灸院も待合室が混み合ったときには、年配のおばあちゃんとかは結構話していますね。全然知らない人同士で「どこが痛いの?」というコミュニケーションが生まれています。
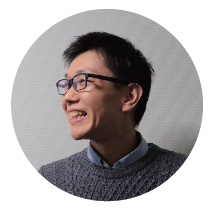
ゆうすけ

山﨑先生
そうやって自分自身のストーリーを話せる場は、やっぱり病院では難しくて、私は開業鍼灸院が中心になると思うのです。
けれども、人によっては東洋医学への疑念がどうしてもあります。それを払拭するのが研究データだと思うので、これからも分野を広げながら、鍼灸の効果を探っていきたいですね。
けれども、人によっては東洋医学への疑念がどうしてもあります。それを払拭するのが研究データだと思うので、これからも分野を広げながら、鍼灸の効果を探っていきたいですね。
「治らない」のは技術的な問題とは限らない
開業鍼灸師として日々、患者さんと対峙していると、どうしても技術的なことばかりに目がいきがちです。今日先生の話を聞いて、ちょっとしたことでも良いから、鍼灸の効果が出やすい工夫を積み重ねていったり、地域のコミュニティの場としての機能に目を向けたりしてもいいんだなと思いました。

タキザワ

山﨑先生
鍼灸師は、全体にとても真面目な性格のように思います。臨床に真面目すぎるがゆえに「治療効果がでないのは、自分の技術が未熟だからだ」と悩んでは、いろんな勉強会で技術を研鑽する方向に行きがちです。もちろん、それも大切なことなんですけど、一方で、患者さんのコンディションや治療院の環境に問題がある場合も少なくないと思うんですよね。
その気付きは、大学院のときに鍼灸でよくならない患者さんをたくさん診てきたのが、原体験としてあるのでしょうか。

ツルタ

山﨑先生
いったん鍼灸治療に対する信頼感が全く持てなくなったのは、大きいと思います。
また、どれだけも研究しても結果が出ない時期もありました。「一体、何が悪いのか? 本当に技術の問題なのか?」と常に考えた結果、「患者さんのコンディションはどうなんだろう?」「伝統的な東洋医学の見方を現代医学的にとらえたときに齟齬が生じていないか?」と考えるようになりましたね。
また、どれだけも研究しても結果が出ない時期もありました。「一体、何が悪いのか? 本当に技術の問題なのか?」と常に考えた結果、「患者さんのコンディションはどうなんだろう?」「伝統的な東洋医学の見方を現代医学的にとらえたときに齟齬が生じていないか?」と考えるようになりましたね。
1周回った感じですよね。鍼灸の限界を感じたことで、より東洋医学の本質的な部分を見直していったといいますか…。

ツルタ

山﨑先生
今は「科学で解明されていないだけで、東洋医学は必ず効果がある」という前提で、予防医学としての東洋医学をいかに実践するかを重視しています。疲労や睡眠、そして美容というウェルビーイングにつながる3分野で、鍼灸がどう貢献できるか。研究で解き明かしていきたいです。
故事成語で「病膏肓に入る」というように「病が深いところに入ってしまうと、手の施しようがない」と、古来の人びとも考えていたわけですよね。難治性の疾患を治療することよりも、予防医学に重点を置くというのは腑に落ちるものがあります。

ツルタ

山﨑先生
これからも、地域でご開業され日々鍼灸臨床をされておられる先生方の治療経験や体験をもとに、研究をおこなっていきたいと考えています。そして研究結果をまた現場にフィードバックしていく。そうすることで、効果がより出やすい鍼灸を広めていきたいですね。
【撮影協力】
明治国際医療大学
明治国際医療大学
1
2