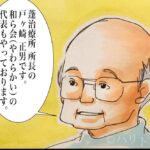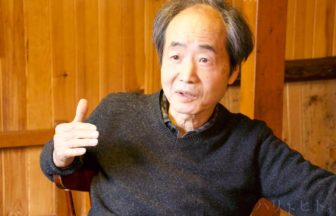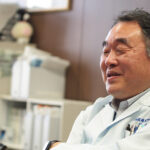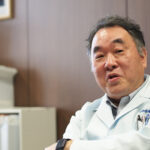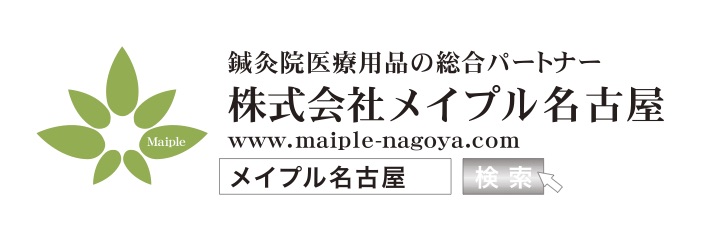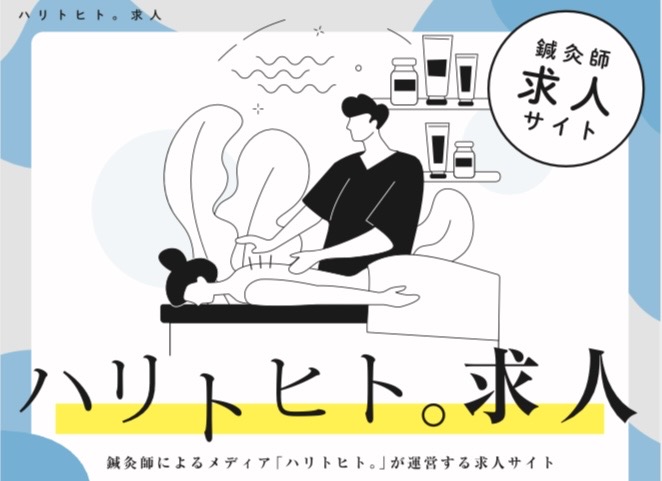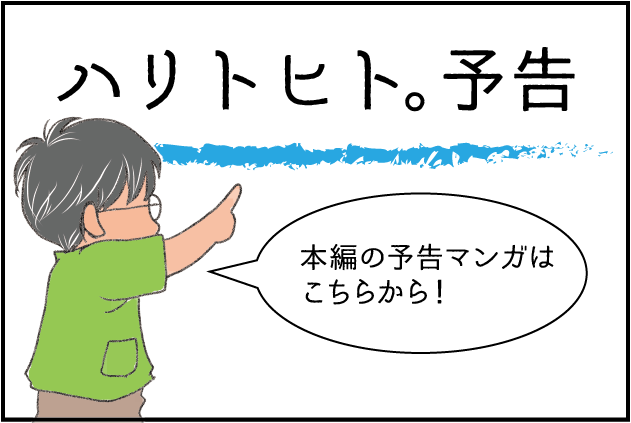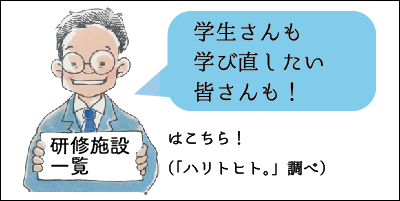経絡治療と太極療法をまとめあげた

先生の著作『思うツボ』(ヒューマンワールド刊)を拝読しました。ツボを立体構造で捉えて4つに分類して、それぞれに適した刺鍼や施灸のやり方がまとまっていました。

ツルタ

戸ヶ崎先生
四型分類を使えば、ツボと鍼灸施術の関係性、その補瀉が整理できちゃうんです。補瀉も僕の独自の補瀉じゃなくて、教科書にあるようなやり方で全部整理できるんですよ。ただ、実践が伴ってないから10年検証をしましたね。ほとんど問題なかった。
10年も検証した。すごいな。

ツルタ

戸ヶ崎先生
大まかにいえば、30代から40代は徹底的に鍼の修行をして、50代近くになって太極治療の概念が加わりました。
体幹部を重視し、さらに中心軸である任脈、督脈を基本に組み立てたシステムで任督中心療法と呼んでいます。具体的には、五臓六腑のアンバランスを整えて、自然治癒力を引きだすというものです。
体幹部を重視し、さらに中心軸である任脈、督脈を基本に組み立てたシステムで任督中心療法と呼んでいます。具体的には、五臓六腑のアンバランスを整えて、自然治癒力を引きだすというものです。
どうして太極治療の概念を取り入れようと思ったんですか。

ツルタ

戸ヶ崎先生
経絡理論を勉強すれば、任脈は陰経の海、督脈は陽経の海ですよね。経絡って任脈、督脈で統合されています。
本来なら中心軸がすごく大事なのに、経絡治療は末梢から動かす方法だからゆえに任脈と督脈を使えなくなっちゃったんですよ。
本来なら中心軸がすごく大事なのに、経絡治療は末梢から動かす方法だからゆえに任脈と督脈を使えなくなっちゃったんですよ。
経絡治療には、任脈と督脈が足りないと思ったわけですか。

ツルタ

戸ヶ崎先生
体幹部のツボを重視する太極治療と、末梢のツボを重視する経絡治療。ふたつの日本鍼灸の重要概念をまとめあげたものが、僕の治療だと思っています。
時系列で過去を治していく

先生っていろんな文献を読んだりとか、すごく座学に熱心だけど、それ以上に実践を大事にしていますよね。

ツルタ

戸ヶ崎先生
そう。僕は実験大好き人間だから、実践ありきですよね。
失敗したことも?

ツルタ

戸ヶ崎先生
もちろん、ありますよ。学生の時に水虫の上にお灸をすると効くって聞いて、実際にやってみたらもっと広がってしまったことがあります。
その経験から、直接より、指の股のちょっと上にくぼみがあれば、そこにお灸をしたらよいことがわかりました。
その経験から、直接より、指の股のちょっと上にくぼみがあれば、そこにお灸をしたらよいことがわかりました。
失敗も学びがあれば、貴重な経験になりますね。治療するのは、やっぱり反応のあるツボじゃないとダメですか。

ツルタ

戸ヶ崎先生
例えば、腰痛に効果があると言われているツボは、たくさん文献を調べてみると70穴以上ありました。それだけあったらどこを使うかなんて誰も決められないんですよ。
たしかにそうかもしれません。

ツルタ

戸ヶ崎先生
そういう意味でも治療点として反応のあるツボを探すことは重要だと思います。それこそ特効穴を1穴か2穴しか知らなければ、悩まなくて済むんですけどね。
いかに探れるか…。

ツルタ

戸ヶ崎先生
そうそう。過去の問題点が、後にいろんなところに症状として出現することもありますよ。複雑な病態であればあるほど何層も過去に症状はさかのぼっていくんです。本質をついた治療ができると、10代の頃にしたケガとかにさかのぼったりもしますよ。
ある意味、それも本治といえそうですね。

ツルタ

戸ヶ崎先生
本治は体のバランス関係を整えるのと時系列で過去を治していく。それが同時に体質改善になるんですよ。
過去もひっくるめて患者さんをみているのか。

ツルタ

戸ヶ崎先生
過去の怪我、事故、手術跡などの影響で不完全治癒になっている場所というのは、結構内部に潜んでいるんですね。そういうのを取り除くのが本治だから。過去を整えていくと結果的に治癒力がかなり発揮される。
最初の原因にアプローチできたらよさそうな感じがします。

ツルタ

戸ヶ崎先生
治療点となる異常なツボも同じく時系列がありますから。異常なツボは発生から段階的に形態を変化させていくんです。病気の変化に従ってツボも変化します。これも四型分類で説明できるんですよ。
「触らなくても感じる」が最終段階
四型分類って1つの鍼灸の体系だと思います。戸ヶ崎先生は流派の初代ってことですよね。

ツルタ

戸ヶ崎先生
先人達が学問的な基本はけっこう整理して資料として残してくれました。こういうのをちゃんと読んだからできたんですよ。だから過去の人達の凄さです。僕は昔から謙虚じゃないけど、これは素直な気持ちで言っています。
次の世代につながる仕事、見習いたいと思いました。

ツルタ

戸ヶ崎先生
鍼灸学というのはまだ発展途上で、学術的には未整理が多いです。そして理論化できない部分が鍼灸には多いからこそ技術を大事にしていると思います。
ツボの反応を捉えるにも、技術が必要ですよね。その技術を得るには、どうすればいいですか。

ツルタ

戸ヶ崎先生
やはり手を作ることだと思います。
僕の作った和ら会(やわらかい)は「鍼灸施術のための手作り」が基本の考え方で、臨床家を育成する真和塾の運営もおこなっています。触診技術だけでなく、伝統医学の概説から刺鍼や施灸の技術も教えているんですよ。
僕の作った和ら会(やわらかい)は「鍼灸施術のための手作り」が基本の考え方で、臨床家を育成する真和塾の運営もおこなっています。触診技術だけでなく、伝統医学の概説から刺鍼や施灸の技術も教えているんですよ。
臨床家には「いい手がある」と聞いたのですが…。

ツルタ

戸ヶ崎先生
いい手は、適度な温もりと柔らかさがあり、手で触れたとき、相手が気持ちよく感じ、同時にあまり意識しなくても相手の反応がわかる手です。
湿っぽく冷たい手や、乾いて硬い手はいい手ではありません。わかろうと意識する手は、いやらしい手なので気持ち悪いです。
湿っぽく冷たい手や、乾いて硬い手はいい手ではありません。わかろうと意識する手は、いやらしい手なので気持ち悪いです。
うーん、どういうことなのか。

ツルタ

戸ヶ崎先生
いい手というのは気が出るんです。だから気が不足しているところに吸い込まれる。気を介して手が吸い込まれるんです。それを感じられる手が最終段階です。体の健康な場所というのは逆に押し返してくるんですよ。邪気があれば、不快で、痛みやしびれを感じたりもします。
厳密には触らなくても感じられるってことですか。

ツルタ

戸ヶ崎先生
そうですね。これは目も同じで、目からも気は出ていますから、相手の気が不足しているところに吸い込まれていくんです。
よく「ツボに指が止まる」って言いますよね。

ツルタ

戸ヶ崎先生
指が止まるのも1つです。それからエアポケットみたいにスッと手が沈み込むとかね。ただ、本当は「手だけでなく、五感を養うことが大切だ」と学生や若手に言いたいです。
感覚の世界、ですか。

ツルタ

戸ヶ崎先生
主観を研ぎ澄ますんです。そうすると自分のものになるし、また、理論化、普遍化も可能です。さらには気の本質に迫れます。面白いでしょう。
鍼灸でずっと自由研究しているんですね。すごく楽しそう。

ツルタ

戸ヶ崎先生
限りなく。だから飽きないですよ。
【記事担当】
取材 = タキザワ・ツルタ
文 = ツルタ
撮影 = ツルタ
編集 = くちやまだ
>> インタビューのダイジェストマンガはコチラ。
>>> 戸ヶ崎先生の選んだ本はコチラ
1
2