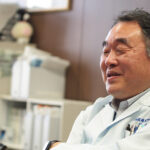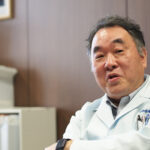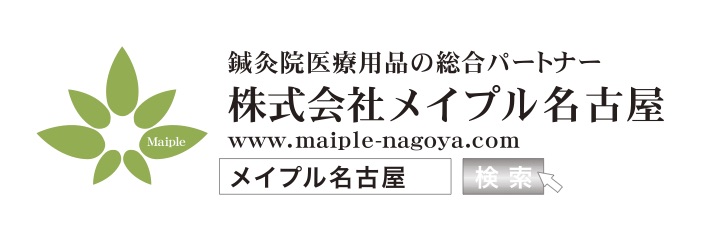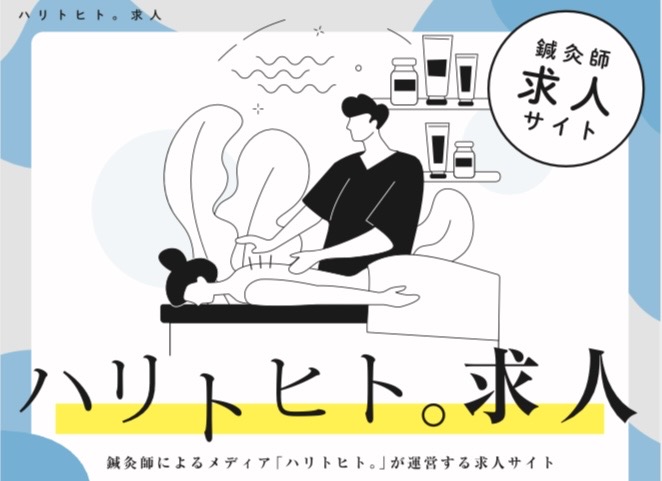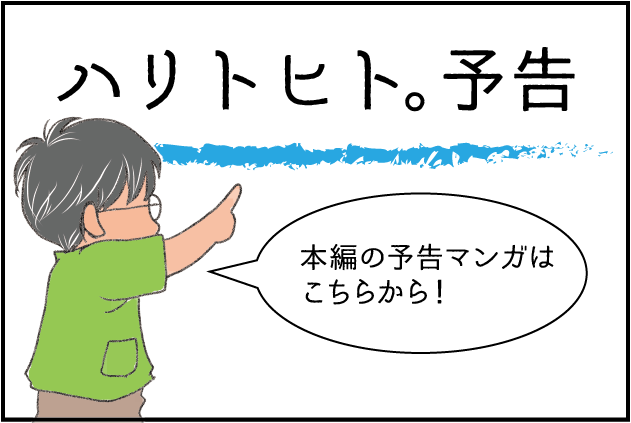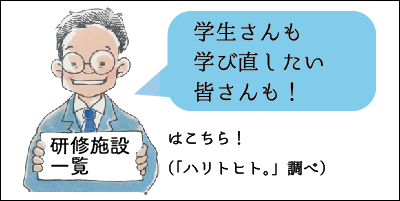ウェルビーイングにつながる「疲労」「睡眠」「美容」の3分野において、鍼灸はどのように貢献することができるのでしょうか。
鍼灸の効果について日々研究を重ねているのが、明治国際医療大学の山﨑翼先生です。意外にも大学院時代に「鍼灸は効かない」と絶望した経験があるといいます。
その後、どんな経験の積み重ねが、今の山﨑先生を形作っているのでしょうか。
インタビューを通じて、鍼灸がより効果を発揮するための環境作りや、地域コミュニティの拠点としての鍼灸院の未来など、研究者はもちろん、開業鍼灸師にとっても役に立つ情報が満載のお話を聞くことができました。
山﨑 翼(やまざき たすく)先生

2005年3月 明治鍼灸大学 鍼灸学部 卒業
2010年3月 明治国際医療大学大学院 博士後期課程 修了 鍼灸学博士
2010年4月 明治国際医療大学 博士研究員
2010年11月 明治国際医療大学 保健・老年鍼灸学講座 助教
2017年4月 明治国際医療大学 鍼灸学講座 助教
2019年4月 明治国際医療大学 鍼灸学講座 講師
2022年4月 明治国際医療大学 大学院鍼灸学研究科鍼灸学専攻専攻長補佐(現在に至る)
2010年3月 明治国際医療大学大学院 博士後期課程 修了 鍼灸学博士
2010年4月 明治国際医療大学 博士研究員
2010年11月 明治国際医療大学 保健・老年鍼灸学講座 助教
2017年4月 明治国際医療大学 鍼灸学講座 助教
2019年4月 明治国際医療大学 鍼灸学講座 講師
2022年4月 明治国際医療大学 大学院鍼灸学研究科鍼灸学専攻専攻長補佐(現在に至る)
大学院では鍼灸の限界を感じた
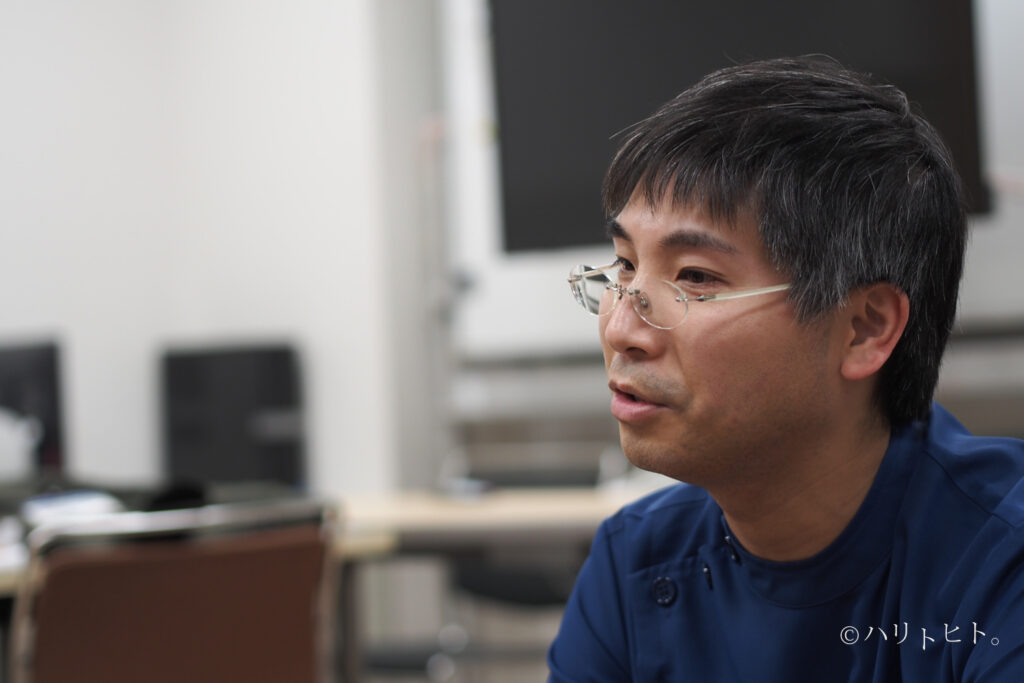
鍼灸師になろうと思ったきっかけを教えてください。
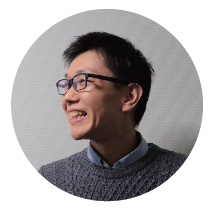
ゆうすけ

山﨑先生
もともとは柔整師になろうと思っていました。学生時代に通っていた接骨院の先生が、とても親身になってくれたんですよね。
でも、当時高校生だった自分が調べた範囲では、柔整よりも鍼灸のほうが、適用範囲が広そうだったので方向転換しました。
でも、当時高校生だった自分が調べた範囲では、柔整よりも鍼灸のほうが、適用範囲が広そうだったので方向転換しました。
適用範囲を調べるところが、先生らしいなと感じました。進学先を明治鍼灸大学(現:明治国際医療大学)に決めるまでにも、入念にリサーチされたんじゃないですか。
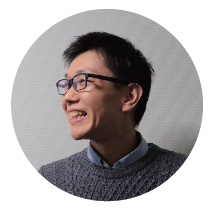
ゆうすけ

山﨑先生
5~6校ほど募集要項を取り寄せました。その中で明治鍼灸大学だけが、パンフレットに鍼灸の適応疾患をかなり細かく羅列してあったんですね。「これだけいろんなものが診られるようになるなら」と進学を決めました。附属病院で卒後研修が受けられるところも、選んだ理由の一つです。
「大学には行ってほしい」という親の希望もあり、鍼灸の専門学校ではなく、明治鍼灸大学に通うことにしました。生まれが茨城なので、京都で一人暮らしをしていましたね。
「大学には行ってほしい」という親の希望もあり、鍼灸の専門学校ではなく、明治鍼灸大学に通うことにしました。生まれが茨城なので、京都で一人暮らしをしていましたね。
鍼灸の4年制大学が明治鍼灸大学しかない時代ですものね。入学後はどうでしたか。イメージとギャップはありましたか。
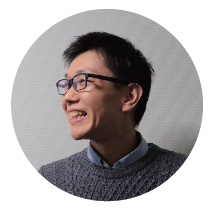
ゆうすけ

山﨑先生
実は鍼を受けたことがなかったので、施術へのイメージがそもそもありませんでした。
当時、関東には関西ほど鍼灸院がなかったんですよね。なので特にがっかりすることはありませんでしたが、東洋医学概論などはワケがわかりませんでしたね。「とりあえずツボを覚えるか」と勉強をスタートさせたことを覚えています。
当時、関東には関西ほど鍼灸院がなかったんですよね。なので特にがっかりすることはありませんでしたが、東洋医学概論などはワケがわかりませんでしたね。「とりあえずツボを覚えるか」と勉強をスタートさせたことを覚えています。
大学院へと進まれたのは、どんな経緯だったのでしょうか。
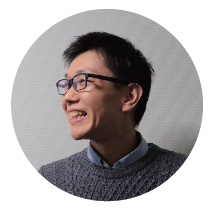
ゆうすけ

山﨑先生
4年生のときにゼミの先生から「臨床系の大学院が新しくできるから」と進められて、その1期生になりました。
さまざまな診療科で勉強をしながら鍼灸の臨床経験を積み重ねていったのですが、大学院2年目のときには、鍼灸治療への期待や可能性を感じることがほぼなくなっていました。
さまざまな診療科で勉強をしながら鍼灸の臨床経験を積み重ねていったのですが、大学院2年目のときには、鍼灸治療への期待や可能性を感じることがほぼなくなっていました。
鍼灸の可能性に目覚めた…のではなくて、ですか。
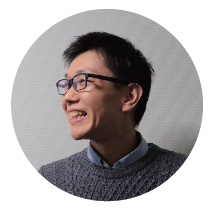
ゆうすけ

山﨑先生
大学院の2年目では、入院患者さん、特に末期がんで終末期の方に対して主に鍼灸治療をおこなっていました。
終末期の患者さんを診るにあたって、自分なりに論文を読んで準備をしたつもりですが、本当に効果が出ない。もちろん、疾患そのものをどうにかできるなんて思っていませんが、症状の軽減すら非常に難しかったです。そんな日々を過ごしていると、「鍼灸治療って効果があるのかな、意味があるのかな」と思うようになりました。
終末期の患者さんを診るにあたって、自分なりに論文を読んで準備をしたつもりですが、本当に効果が出ない。もちろん、疾患そのものをどうにかできるなんて思っていませんが、症状の軽減すら非常に難しかったです。そんな日々を過ごしていると、「鍼灸治療って効果があるのかな、意味があるのかな」と思うようになりました。
「疲労」の研究から「睡眠」さらに「美容」へ
鍼灸に絶望しながらも、その後に博士課程へと進まれたのはなぜですか。
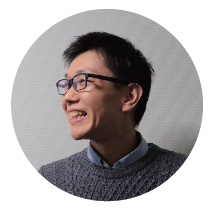
ゆうすけ

山﨑先生
大学院は修士までにして就職しようと思っていたのですが、深夜に教授に呼び出されて「博士課程の進学を真剣に考えるように」と言われたこともあって、当時関心のあった慢性疲労症候群や慢性疲労の研究をやろうと、博士課程に進むことにしました。
研究は、当時京都府立医科大学大学院医学研究科免疫・微生物学教室で教授をしておられた今西二郎先生のもとで指導を受けながら研究を進めていきました。
研究は、当時京都府立医科大学大学院医学研究科免疫・微生物学教室で教授をしておられた今西二郎先生のもとで指導を受けながら研究を進めていきました。
慢性疲労に鍼の可能性を感じていたのでしょうか。
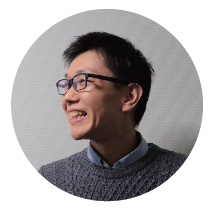
ゆうすけ

山﨑先生
いえ、そうではなくて、社会に還元できる研究テーマを考えたときに、疲労についてきちんと勉強したいと思いました。疲労についての先行研究にいろいろあたっていくと、結局は睡眠の問題にいきつくわけです。「睡眠の質を高めないと疲労はとれない」と、博士課程では疲労と睡眠をセットで研究していました。
その後はどのように研究は発展しましたか。
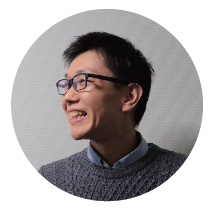
ゆうすけ

山﨑先生
博士課程を修了したあとは、博士研究員として半年くらい研究を続けました。
博士研究員では、個人の探究心だけでなく「鍼灸業界全体に資する研究をおこなわなければならない」と感じていましたので、当時はまだ論文がなかった美容鍼灸の研究を行うことに決めました。
博士研究員では、個人の探究心だけでなく「鍼灸業界全体に資する研究をおこなわなければならない」と感じていましたので、当時はまだ論文がなかった美容鍼灸の研究を行うことに決めました。
美容をテーマに選ばれたのは、意外な気がします。
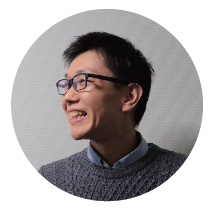
ゆうすけ

山﨑先生
もともと美容鍼灸には否定的でした。当時は科学的な根拠に乏しいのに広告が先行していた印象があって、「そんなに効果があるわけないだろ」と厳しい目で研究を始めたんですけど、何回やっても効果は出るんですよね。
それであれば、裏づけとなるデータをとりたいと思ったんです。
それであれば、裏づけとなるデータをとりたいと思ったんです。
これまで取り組んできた疲労や睡眠のテーマともかかわってきそうですね。
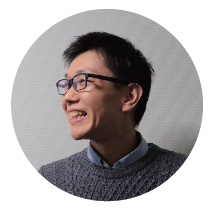
ゆうすけ

山﨑先生
人が疲労を感じるのは、酸化ストレスが溜まるからとされています。良質な睡眠がとれれば、寝入りの3時間ぐらいで成長ホルモンが一気に放出されて、酸化ストレスが減少し、疲労が回復するとされています。つまり、寝入りの睡眠の質をいかに良くするかが、研究の焦点になってくるわけです。この成長ホルモンが皮膚代謝にも大きく影響しているため、よく寝られている人じゃないと、皮膚はキレイにならない…。
すべて関係してくるってことですね!
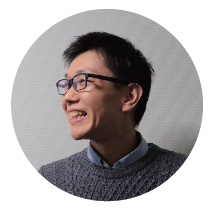
ゆうすけ

山﨑先生
つまり、よく眠るための鍼灸ができれば、疲労・睡眠・美容はすべてよい状態になるので、それがどんな鍼灸かというのを追求しているのが現状です。
食べすぎの背景に寝不足があることも
疲労や睡眠へのアプローチは、鍼灸師の仕事の究極みたいな感じがするんですよね。もともと人に備わっている治癒力を高めようとか、養生みたいな…。

ツルタ

山﨑先生
「よく食べ、よく出し、よく寝る」が健康の基本ですよね。
最近は気候変動や冷たい飲食物の摂取過多を含め、古典で言われるような季節に適した暮らしをするのが困難になっています。季節からズレてしまった人の生体リズムをどう捉え、どう治すかというのは、私達鍼灸師全体の大きなテーマじゃないかと感じています。このあたりは、経絡治療の先生方が非常に詳しく、お話させていただくと大変刺激を受けます。ただ、気候変動はもとに戻せませんから、いかに身体を今の状況にマッチさせるか、そのためのサポートを鍼灸師がどうやるかがポイントになってくるのだと思います。
最近は気候変動や冷たい飲食物の摂取過多を含め、古典で言われるような季節に適した暮らしをするのが困難になっています。季節からズレてしまった人の生体リズムをどう捉え、どう治すかというのは、私達鍼灸師全体の大きなテーマじゃないかと感じています。このあたりは、経絡治療の先生方が非常に詳しく、お話させていただくと大変刺激を受けます。ただ、気候変動はもとに戻せませんから、いかに身体を今の状況にマッチさせるか、そのためのサポートを鍼灸師がどうやるかがポイントになってくるのだと思います。
食については、どのように考えていますか。

ツルタ

山﨑先生
寝ていないと人間の体は、脂肪細胞から分泌されるレプチンの量が減少して、グレリンという食欲増性物質が増えるとされています。おそらく休養できていない分を食べて補おうとする反応だと思うのですが、このグレリンが脳の味覚を感じる部分に作用して、脂っこいものをとにかく美味しく感じるようにしてしまうとされています。
無性にポテトチップスが食べたくなるときがあります!

ツルタ

山﨑先生
エネルギー源として油はコスパが良いので、できるだけ油をおいしく感じるように、脳の味覚が変更されてしまうともいわれています。ですが、脂っこいものを食べ過ぎると胃腸の調子は悪くなり、合わせて偏った食生活は腸内細菌のバランスにも影響するとされています。腸内細菌の環境悪化は精神状態や睡眠状態にも影響しますので、結果的に寝つきも悪くなって…。そんな「負のサイクル」を止めるためにも、食事と睡眠の関係も大切です。
単に「食べすぎないように」ではなくて「よく寝るように」という指導ができるわけか…。その知識があるとアドバイスの質が良くなりますね。

ツルタ

山﨑先生
鍼灸の施術と関係するところでいえば、側頭筋・咬筋・オトガイ筋など顔面部や頸部の筋肉が緊張していると、睡眠中に覚醒脳波が出てくるため、どうしても睡眠の質が下がりますね。
美容鍼は顔への刺鍼を重視しますよね。

ツルタ

山﨑先生
顔に鍼を打つと、咬筋や側頭筋の緊張が取れることで睡眠の質が改善されて、美容効果にもつながると思われます。顔面部への美容鍼はその点でも、理に適っていると思います。
臨床でも、鍼の途中で寝ちゃう人がすごく多いです。顔面部や頸部が緩むことで、リラックス効果が高いんでしょうね。

ツルタ

山﨑先生
ほかには、無味無臭よりも好きな香りを嗅ぎながら就寝したほうが、睡眠の質がよくなるといったデータもあります。患者さんによって、灸施術のモグサの香りが快眠へと導いてくれる可能性はあります。
香りも鍼灸院の環境整備につながってくるわけですね。ハリトヒト。鍼灸院では、照明を工夫していて、整形外科的な訴えの場合は白色の電球で病院に近い雰囲気に、気分障害のような精神的な訴えの場合は暖色系の照明にしてゆったりとした雰囲気にするようにしています。

ツルタ

山﨑先生
すごくよいと思います。一般的に白色光は人を興奮させて、オレンジ色の光のほうが、鎮静作用が働くとされています。大変理に適っていると思います。
NEXT:鍼灸院を地域コミュニティの拠点にしよう
1
2